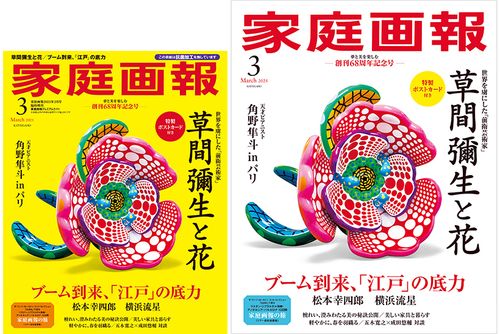〔特集〕思い出の地、パリで独占取材 進化し続けるピアニスト角野隼斗(前編) 2024年世界デビューを果たした、話題のピアニスト・角野隼斗さん。東京大学大学院卒業という異色の経歴、ショパン国際ピアノコンクールセミファイナリスト、YouTubeチャンネル登録者数143万人を超えるCateen(かてぃん)、シティソウルバンド「Penthouse」のメンバー──、ジャンルや国を超え人々を魅了する姿を、大学院生時代に留学していたパリで追いかけました。
音を物理的に解釈する。パリでの研究の思考が感覚を裏付けてくれた

「ポンピドゥー・センター」は角野さんにとってパリ留学中の思い出の場所。2025年9月から2030年まで改装工事のために4〜5年間の閉館が予定されている。パリのパノラマが一望できる最上階のチューブ形の通路にて。
角野隼斗さん(すみの・はやと)1995年千葉県生まれ。東京大学工学部卒業。東京大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。2018年、東京大学大学院在学中にピティナピアノコンペティション特級グランプリ受賞。2021年、ショパン国際ピアノコンクールセミファイナリスト。2024年3月、ベルリンに本拠を置くソニークラシカルと日本人4人目の世界契約。同年10月、世界デビューアルバム『Human Universe』を発表。オリコン週間総合アルバムチャートで7位を記録するなどクラシック音楽作品として異例のヒットとなっている。
パリコンサートの衣装は「アルマーニ」。思い出の場所では「E S:S」のコートを。 大学院生時代に留学した 秋から冬へのパリ
2023年4月から東京とニューヨークで二拠点生活をしている角野さんですが、パリはとても縁の深い場所です。東京大学大学院生だった2018年、フランスに留学しています。

「留学していた研究所があるこの界隈はパリの中でも特に思い出深い場所です」
角野さんが5か月間通ったフランス国立音響音楽研究所(IRCAM)があるストラヴィンスキー広場。ポンピドゥー・センターのすぐそばで、石畳の路地と壁の現代アートが独特の雰囲気を醸し出している。
院生時代の研究テーマに、AIを用いた自動採譜、自動編曲などがありますが、その分野で先進的な研究機関として知られるのが、フランス国立音響音楽研究所(IRCAM)。ポンピドゥー・センターのすぐそばにあります。9月から翌年1月まで、シテ・ユニヴェルシテール(国際大学都市)の宿舎からその研究所に通うのが角野さんの日課でした。
「バゲット・トラディションと『エシレ』バター、ソシソン(サラミ)で食い繫いでいました」と、角野さんは笑います。
「パリ市庁舎のそばに研究所員が使える学食のような食堂があって、しっかりしたランチをとても安く食べられました。そして夜に予定がなければ、その質素な食事で……。宿舎に共同のキッチンがあったのですが、自炊することはほとんどありませんでした。ゆで卵を作ろうとすると、どういうわけか僕はいつも割ってしまう(笑)。あと、ワインを飲むようになったのはパリに来てからのことです」。

「研究所の人たちと一緒に、帰りがけ、ここに並んだカフェのどこかに入ってビールを飲んだりもしました」。数々の現代アート作品が水辺を彩るストラヴィンスキー広場前のカフェにて。午後にはますます活気を帯びる。
ボージョレーヌーヴォーの解禁を学食で祝ったのも留学中の思い出。クリスマスには研究所に誰もいないという寂しさを感じることはあったとしても、この留学期間がパリを特別な場所にしているようです。
音の「色」についての考えを より深めることに

ポンピドゥー・センターのエスカレーターにて。「夏はすごいんです。ここは温室効果でとても暑くなるんです」と、角野さん。留学中の記憶を懐かしそうに語ってくれた。
IRCAMでの経験は今どのように生かされているのか尋ねると、角野さんは真摯に言葉を選ぶようにしながら次のように答えてくれました。
「もっと時間があったら研究を深めて直接何かの形でそれを発表できたかもしれません。けれども、研究中の思考は音楽家となった今の僕に影響していると思っています。音というものを計量的、物理的に解釈する。それが今まで感覚的にしてきたことの裏付けとなって、表現をするうえでの判断がより強固なものになりました」
さらに、ピアノの音色についてとても興味深い話をしてくれました。
「声とかバイオリンとかと違って、ピアノは鍵盤を押すだけですから、そんなに機能的にバリエーションはないはずなのです。けれどもピアニスト全員、違う音色を持っている。それはどういうことなのか? 一口に音色といっても二つの方向性があって、一つの音の中で生まれるものと、複数の音のバランスのコンテクストの中で生まれるものがあると思う。色もそうです。単色の色そのもの、そして周りの色との組み合わせで同じ色でも汚く見えたり、綺麗に見えたりします。
例えば和音のバランスなどもそうですし、絶妙な時間の差によっても、その聞こえ方が変わる。それを音色と形容するけれども、実は音色ではなかった。音量のバランスとタイミング。ちょっとタイミングを遅らせたり、オクターブをちょっとずらすだけで、感覚的には音色が変わったように聞こえる。ピアノという楽器は、10本の指で弾くわけですから、その組み合わせにはものすごい選択肢、可能性があるわけです。音色のパレットを増やすために、鍵盤の上で指をどう動かすかを考えるだけでなく、いろいろなアプローチがある。それはIRCAMでの研究を通して学んだことです」

撮影中、内側からあふれ出る音楽に合わせるかのように、角野さんの指先や体が自然と動くシーンが幾度も見られた。
(次回へ続く。)

 角野隼斗さん(すみの・はやと)
角野隼斗さん(すみの・はやと) 院生時代の研究テーマに、AIを用いた自動採譜、自動編曲などがありますが、その分野で先進的な研究機関として知られるのが、フランス国立音響音楽研究所(IRCAM)。ポンピドゥー・センターのすぐそばにあります。9月から翌年1月まで、シテ・ユニヴェルシテール(国際大学都市)の宿舎からその研究所に通うのが角野さんの日課でした。
院生時代の研究テーマに、AIを用いた自動採譜、自動編曲などがありますが、その分野で先進的な研究機関として知られるのが、フランス国立音響音楽研究所(IRCAM)。ポンピドゥー・センターのすぐそばにあります。9月から翌年1月まで、シテ・ユニヴェルシテール(国際大学都市)の宿舎からその研究所に通うのが角野さんの日課でした。 ボージョレーヌーヴォーの解禁を学食で祝ったのも留学中の思い出。クリスマスには研究所に誰もいないという寂しさを感じることはあったとしても、この留学期間がパリを特別な場所にしているようです。
ボージョレーヌーヴォーの解禁を学食で祝ったのも留学中の思い出。クリスマスには研究所に誰もいないという寂しさを感じることはあったとしても、この留学期間がパリを特別な場所にしているようです。 IRCAMでの経験は今どのように生かされているのか尋ねると、角野さんは真摯に言葉を選ぶようにしながら次のように答えてくれました。
IRCAMでの経験は今どのように生かされているのか尋ねると、角野さんは真摯に言葉を選ぶようにしながら次のように答えてくれました。