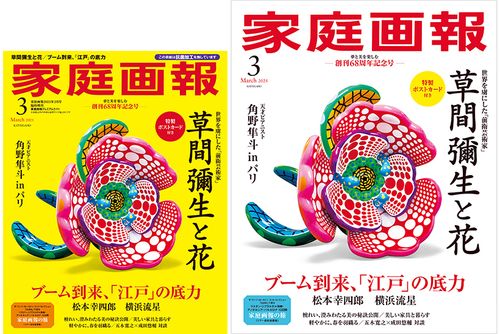〔特集〕学習院コレクションより 華麗なる皇室文化の象徴 高貴なドレス ローブ・モンタント 収蔵作品25万点以上を誇る学習院コレクション ── 。日本の歴史と伝統文化を知るうえで欠かせない皇族・華族ゆかりの品々から、以前は「ボンボニエール」を紹介しましたが、今回は「ドレス」を取り上げます。上皇后陛下から下賜されたローブ・モンタントなど、優雅で気高さに満ちた服飾の世界をお楽しみください。
・
特集「ローブ・モンタント」の記事一覧はこちら>>>
※「作品名」の次の行は、ドレスが下賜された時期を記しています。 皇后陛下が率先した洋装着用への決意
明治維新後の激動の中で、一番大きな変化があったのは、実は皇室かもしれません。それまで京都御所の御簾の内で限られた方々とのみお会いになっていた明治天皇は東京へ移り、西欧諸外国の賓客接遇のために洋装礼服を取り入れたのでした。礼服が洋服と定められたのは明治5(1872)年11月12日。この日は現在「洋服記念日」になっています。
一方、皇后(昭憲皇太后)の洋装化には時が必要でした。大日本帝国憲法公布が間近に迫った明治19年、西欧列強に引けを取らない国家樹立のため、伊藤博文首相・皇后宮大夫香川敬三などより洋装化をすすめられた皇后は「国のためであれば何でもする」と決断されます。
いわゆる十二単に檜扇で容貌を秘していた当時の皇后が、肌を露出したドレス姿で人前に出ることには大変な勇気が必要だったと思われます。国のために一歩前に進まれた皇后の決意は並々ならぬものでした。遂に明治19年7月30日、皇后は華族女学校の卒業式にドレスを着用し、初めて人前にお出ましになりました。日本女性の近代化の幕が開けたのです。
翌20年の新年拝賀儀式から、皇后はじめ皇族妃は洋装大礼服で臨むこととなりました。この直後に皇后は「洋装は日本古来の『衣(ころも)』と『裳(も)』と同じであるから、洋装は理にかなっている。ただし、服を作る際には国産の生地と技術を用いること」という内容の「思召書」を発します。
高松塚古墳の壁画のような古代女性の服装は、西洋の上着とスカートのセット・アップに確かに似ています。洋装化に躊躇する人々の心のハードルを下げる意図が感じられます。そして、何より、ドレス制作であっても、国産の生地を使用し、織りや刺繡などは日本の伝統技法を用いることを推奨し、日本の伝統工芸技術や職人たちを守ろうとしたのです。
この皇后の思し召しは現在の皇室にも受け継がれています。上皇后陛下のローブ・モンタントには佐賀錦が用いられ、令和6(2024)年6月に皇后雅子さまがイギリスを訪問された際も、カミラ王妃へ佐賀錦のハンドバックが贈られました。明治天皇の皇后の並々ならぬ決意が日本皇室の伝統となっているのです。
【上皇后陛下】
 ローブ・モンタント
ローブ・モンタント
平成時代 上皇后陛下より学習院へ下賜佐賀鍋島藩で生み出された伝統的織物である佐賀錦を用い胸もととウエストから裾にかけて花文様が表現されている。肩からマントを流すデザインは上皇后陛下のお好みである。平成10(1998)年のデンマークご訪問などでお召しになった。
上皇后美智子さまは、お会いになるお相手やシーンに応じてお召し物を選ばれるとともに、日本の伝統技術を生かすことに心を配られているそうです。このドレスにちりばめられた花文様は、伝統織物である佐賀錦を葉や花びら形に切り抜き、その縁取りや茎部分を金糸、銀糸を用いて、日本刺繡の技法である駒繡ぬいで留め付けています。




(次回に続く。
この特集の記事一覧はこちらから>>)

 ローブ・モンタント
ローブ・モンタント


 (次回に続く。この特集の記事一覧はこちらから>>)
(次回に続く。この特集の記事一覧はこちらから>>)